
なぜここで滑落、転落?という場所で事故は起きます。何万人もの登山者が、何万歩も岩稜帯を歩けば、そのうちのたった一歩が安全の閾値を超えて、取り返しのつかない事態を招きます。
そのうちの数パーセントは、靴紐の蝶結びを「足元の枝にひっかけた」「反対側の靴のフックにひっかけた」という事例が含まれているのではないか、と筆者はニラんでいます。
自分自身、20~30代の血気盛んな頃、いい加減な靴紐の結び方で岩稜を駆けるように歩き回っていたことを思い返すと、ゾッとします。
余った靴紐を足首に回してから蝶結びするのが小粋だと信じていました。

涸沢岳頂上にて
現在、筆者は高尾山を登るときでも、こんな靴紐の結び方をしています。
- まず、普通に蝶結びします。蝶結びの輪が大きいのが気になります。

- 蝶結びの輪をフックにかけて引き絞ります。

- 両方ともフックにかけると、こうなります。靴紐がかなり余るのが気になります。

- もう一回、蝶結びします。蝶結びの輪をまたフックにかけます。最上段のフックが満員御礼なら、ひとつ下のフックにかけます。

- 完成の図。4箇所がフックにかかっています。

ここまですれば、転倒・転落の事故の可能性を数パーセント減らすことができるでしょう。
3.で靴紐が余らないように、ちょうど良い長さの靴紐に交換することも検討したいところ。ただし、ちょうど良いくらいの長さだと、靴紐の末端を手に巻き付けて、力を込めて締めるという方法はとりにくくなります。
さて、安全意識が高まったところで、山に出かけましょうか。
先年の冬、八ヶ岳に出かけた時のこと。筆者はいつも通り、リラックスモードで茅野駅のコンコースを歩いていました。フック部分の靴紐を解いて、足首にひと回しして、軽く蝶結びしています。

すると突然、足が何かに引っかかりました。反射的に足を前に出してバランスをとろうとしますが、両足どうしがくっついて離れません。まるで棒のように倒れて、地面に右肩を痛打しました。
ゆるゆるの靴紐が、反対側の登山靴のフックに引っかかったようです。広々とした廊下のような場所だったのが不幸中の幸いでした。もし階段を下りているときだったら、重傷を負っていたと思います。
そのあと入山したわけですが……。登山口で靴紐をしっかり締め上げることができないくらい右肩が痛みました。ロングスパッツやアイゼンを装着するのも一苦労でした。
2ヶ月くらいの間、日課のおざなりストレッチング(15分くらい)や、ジムでのボルダリングで、思うように体を動かせず、不自由しました。
以降、入山前、下山後のリラックスモードでも、靴紐をゆるめすぎないように気をつけています。


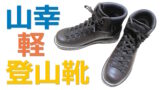
コメント